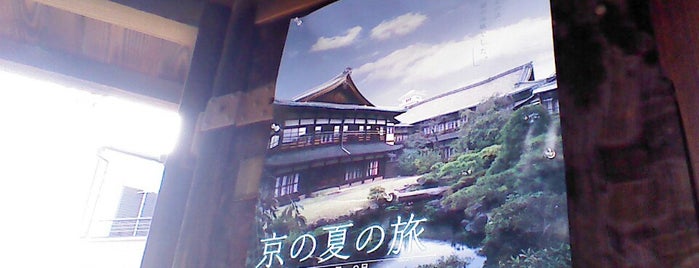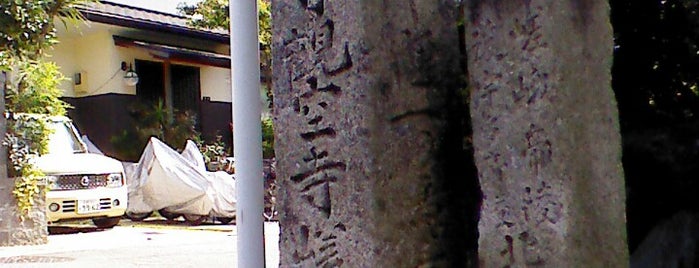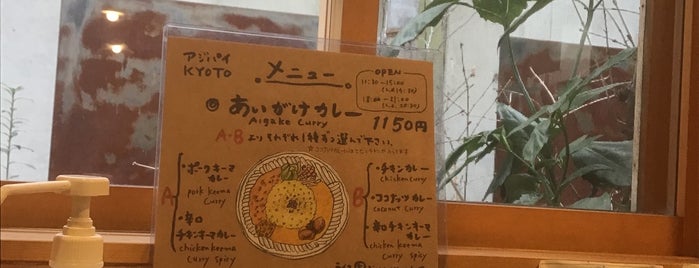立てた京都2
Created by k̦̮̮̭̰̪̩͇͓̦͒̂̓͐̽̆̉̊̇͒o̳̙̣̲̞̠̙͖̖͖̩͗̈́͛͆̃͋̊̔̒̓̀̏r̩̜̙͖̠̪̫͖͖̖͖̐̌̐̾̿͊y͕̬̯̠͙̬̓̏̒̂̎̑̎̾̒͗́ͅu͇͔̞̞͖͉̞͊̌͋̈̄̀̅́̿ m̙̗̱͇͕̟̀̈́͛͂̐̽̋͌̄̚̚ͅó͕̙͔͍͙͖̘̳̳̗̆͊̾͊̉́n̠̠̤̣̮̰̙͌̇̄̾̑̏̾̅̔̋̆̚ͅ • Updated On: March 10, 2024管理用。
Foursquare © 2025 Lovingly made in NYC, CHI, SEA & LA