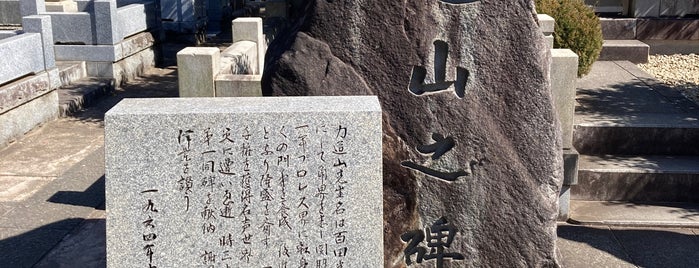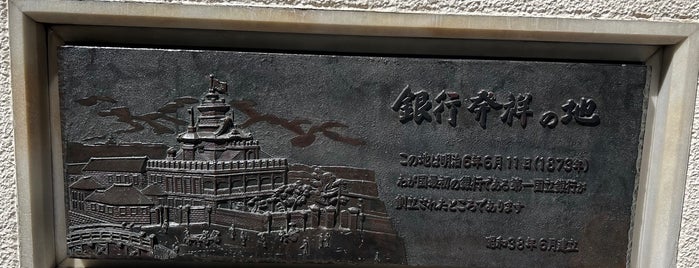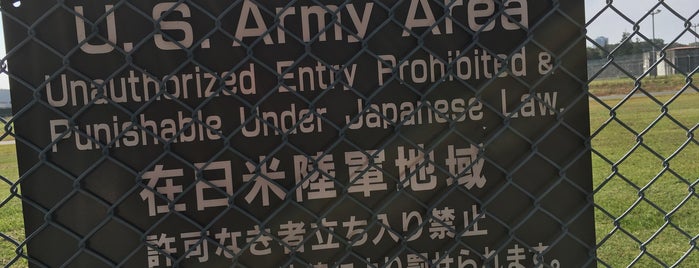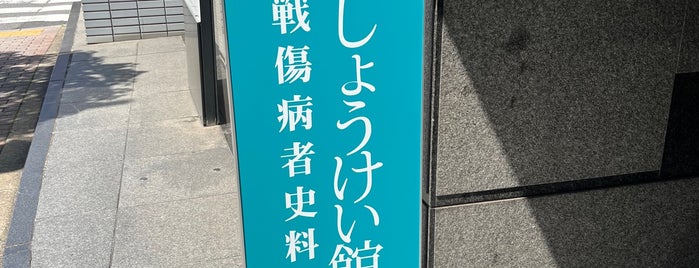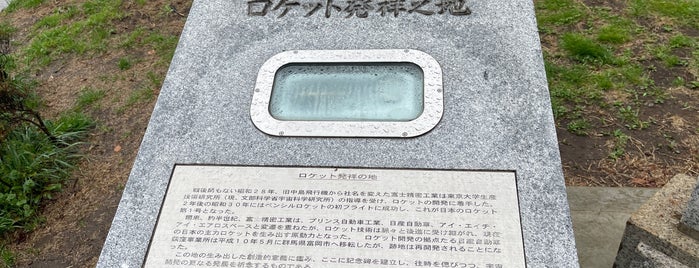![]() ここはかつて、茨城北部から福島南東部に広がる常磐炭田の一部でした。石炭が主流だった時代、このあたりは首都圏に最も近い大規模炭田として日本の発展を支えてきました。市内のいたる場所でその名残が見られますが、ここにあるのは元石炭積込場の貯炭場跡です。コンクリート製の四角い建築物がとても印象的です。 【茨城県北ジオパーク】 Read more.
ここはかつて、茨城北部から福島南東部に広がる常磐炭田の一部でした。石炭が主流だった時代、このあたりは首都圏に最も近い大規模炭田として日本の発展を支えてきました。市内のいたる場所でその名残が見られますが、ここにあるのは元石炭積込場の貯炭場跡です。コンクリート製の四角い建築物がとても印象的です。 【茨城県北ジオパーク】 Read more.
![]() 山手111番館の建物は横浜山手聖公会やベーリックホール、根岸競馬場観覧席などで知られるアメリカ人建築家J.H.モ-ガンの設計によるもので、1926年(大正15年)に当時横浜で両替商を営んでいたラフィンの居宅として現在地に建築されたものだという。 Read more.
山手111番館の建物は横浜山手聖公会やベーリックホール、根岸競馬場観覧席などで知られるアメリカ人建築家J.H.モ-ガンの設計によるもので、1926年(大正15年)に当時横浜で両替商を営んでいたラフィンの居宅として現在地に建築されたものだという。 Read more.
![]() 「山手イタリア山庭園」の一角に「外交官の家」が建っている。この建物はもともとは1910年(明治43年)に渋谷の南平台に建てられ、内田定槌(さだつち)の私邸として使われていたものだ。内田定槌は明治から大正にかけての外交官で、そこから「外交官の家」の名がある。 Read more.
「山手イタリア山庭園」の一角に「外交官の家」が建っている。この建物はもともとは1910年(明治43年)に渋谷の南平台に建てられ、内田定槌(さだつち)の私邸として使われていたものだ。内田定槌は明治から大正にかけての外交官で、そこから「外交官の家」の名がある。 Read more.
![]() この一帯はかつて原善三郎や茂木惣兵衛といった明治期の横浜の豪商が邸宅を構えていた場所だったが関東大震災によって壊滅、その後の復興事業として旧野毛山貯水池や病院などの跡地とともに公園として整備されたものだ。 Read more.
この一帯はかつて原善三郎や茂木惣兵衛といった明治期の横浜の豪商が邸宅を構えていた場所だったが関東大震災によって壊滅、その後の復興事業として旧野毛山貯水池や病院などの跡地とともに公園として整備されたものだ。 Read more.